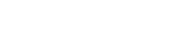友人には、「あと一人か二人連れてきて!」と事前にメールをしておいた。
このレストランの料理を楽しむには三人以上が理想。そして何より、そういう誘い方をすれば、彼が最近やっと出会えた新しい「ガールフレンド」を連れてくるだろうと思った。
シンガポールの「ディムサム」は、日本では飲茶とか点心と呼ばれているモノと同じ。中国の本場では、積み重ねられたセイロで熱々に蒸し上げられたショーロンポーなんかを、朝食感覚で、お茶を飲みながら大勢でゆっくり楽しむのが伝統のはずだけど、シンガポールのディムサムは、ほぼ24時間アクセス可能。夜遊び帰りの20代30代が深夜に群がるスポットだ。
この街の人気店の多くは、フラっと立ち寄ることができない。事前に計画を立て、混む時間の前を狙うか、長蛇の列を辛抱して待つ体制を整える必要がある。友人とは、19時にお店で、と約束していたのだが、18時半に彼からのメッセージ。
「番号が取れた。テーブルは36番。」
計画性に優れた彼らしい動きに感心した。
この店は、列に並ぶのではなく、受付でiPadに携帯番号を入力する。テーブルが用意されると、自動的にSMSが返信される仕組みになっている。何年も改装していない古臭い店のわりに、最新のテクノロジーを導入して効率化を図っているあたりがシンガポールらしい。そして、そんなハイテクな流れについていける中高年もたくましい。友人を待たせてはいけないと、地下鉄を降りて、Uberを呼んだ。
テーブルでは、友人と、その隣にはキャミソールに長くてゆるいウェーブの髪が揺れる白人の女の子が座っていた。待たせてごめんね!はじめまして、と急いで席に座りながら簡単にファーストネームを交換するような自己紹介を終えると、友人は私にこう言った。
「この子はね、まるでここの奶黄流沙包(カスタード饅)みたいなんだよ。」
友人が続けてなんて言おうとしているのか、完全にわかっていたけど、あえて最後まで聞いた。
「外側は真っ白の白人だけど、中身は真っ黄色。完全に中国人。俺は、アジアの食べ物を怖がって食べない欧米人の女は大嫌いだけど、この子はなんでも食べるから中国人みたいで最高なんだ」
「カスタード饅」と言われた彼女は、目を細めて笑っていた。
大学生の頃、東京にやってきたアメリカ人の白人女子が、海藻サラダにトッピングされたシラスを見て、「目玉のついている生き物がこんなにたくさん乗っているもの食べられないわ!」と泣きわめいた時のことを思い出した。食文化は、幼い頃から身体に染み付いているもの。きっと、それはキリスト教徒にとっての祈りの言葉のようなもので、毎日それを頼りに生きている有難いモノを怖がられたり、拒否されたりすると、なにか大切な宝物を目の前で乱暴に踏みにじられたような感覚になる。友人にとっても、私にとっても、自国の食文化を含め、「アジアの食」はとても大切なもので、音楽イベントのためにみんなで近隣の国へ飛んだ時も、何を食べるかは慎重に話し合って計画して、どれだけ身体が疲れていても、いつも有難く、楽しく食べる。その土地の人々が昔から大切にしている料理をいただくことは、未知なる文化を一番簡単に体験できる方法だと思う。その簡単な一歩すら踏み出さない人をパートナーにしたら、大冒険は始まらないだろう。
カスタード饅は、7、8皿目にようやく私たちの前に現れた。小さくて、まん丸なカスタード饅が三つ、セイロの中で湯気を発している。
指先を軽く火傷することは承知の上で、ふんわり柔らかな皮を慎重に割っていく。中からは、眩しいほどに真っ黄色のカスタードが溶岩のように噴出する。一滴でも逃したら絶対に後悔する。名前の通り、中国の塩漬け玉子から作られているトロトロのカスタードは、甘さと塩っぱさと旨味が凝縮されているのだ。
食事を終えた友人は、真っ白なTシャツがはち切れそうなほど真ん丸なお腹をしていた。そういえば久々に見る彼の笑顔は、顎のラインがすっかり首と一体化している。あなたも十分カスタード饅じゃないかと言いたい気持ちを抑える。
多少の火傷は覚悟で、新な冒険に手を伸ばす。幸せ太りとは、そういう勇気ある行動の結果なのだろう。
*****
シンガポールの地元民が推薦する美味しいスポット、下記のサイトでもたくさん紹介しています。見てね。